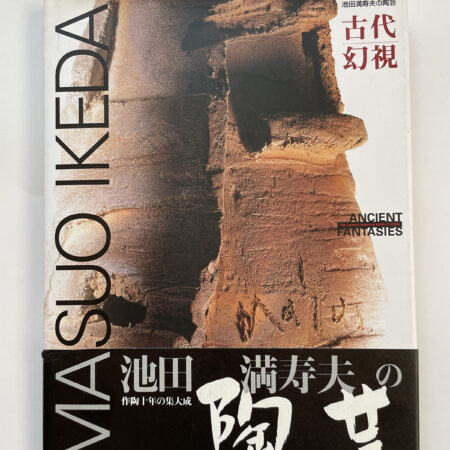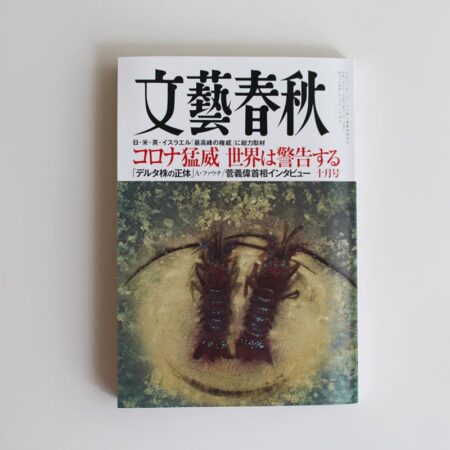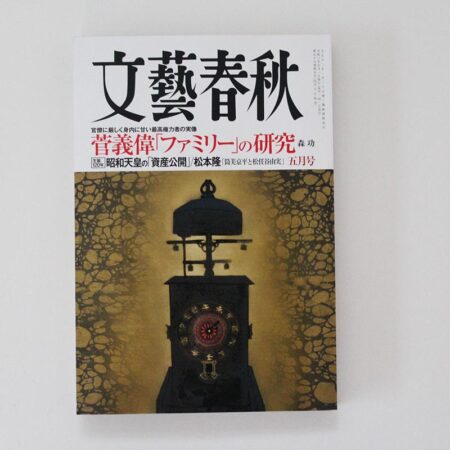黄梅院の後は、加賀前田家ゆかりの塔頭・興臨院へ。
庭が素敵で、作庭の参考になり、見ていてワクワクします!

興臨院は、1520年代に能登国の守護大名・畠山義総によって、大徳寺第86世・小渓紹怤(仏智大通禅師)を開祖として建立された塔頭で、以後、畠山氏の菩提寺となっています。
「興臨院」の寺名は、義総の法名である「興臨院殿伝翁徳胤大居士」から付けられたそうです。
本堂は創建直後に焼失しましたが、すぐに再建され、現存する本堂は天文2年(1533)頃のものです。

畠山家が没落の後の天正9年(1581)には、戦国武将・前田利家によって本堂屋根の修理が行われ、以後は前田家の菩提寺となります。
昭和50年より3年間にわたって、本堂、唐門(玄関)、表門などの解体修理が行われ、再建当時の姿に復旧されました。そして、この時、庫裏も新設。
一重入母屋造で方丈形式の本堂(重要文化財)は、室町時代の建築様式の特長をよく表していて、檜皮葺の屋根は近代の寺院より低く、優美で安定感があります。
内部は、簡素で質素。
床の間は日本で最初のものであるといわれています。

方丈前庭は、昭和の解体修理の完成に合わせて、資料を基に作庭家の中根金作によって復元されたものです。
この庭は、寒山拾得が生活をしていた天台山の国清寺の石橋を模し、大石や松をあしらって理想的な蓬萊の世界を表現しているそうです。

前庭の西方には、バイタラジュ(貝多蘿樹)が植えられています。貝多蘿樹とは、梵語で“木の葉の意味。
貝多蘿樹の葉は古代インドでは、竹筆で経文を書写するのに用いられていたため、仏家では珍重されていました。

方丈の裏庭や、坪庭も素晴らしく、いつまでも見ていたい魅力に満ちていました。



◎大徳寺 興臨院
京都府京都市北区紫野大徳寺町80